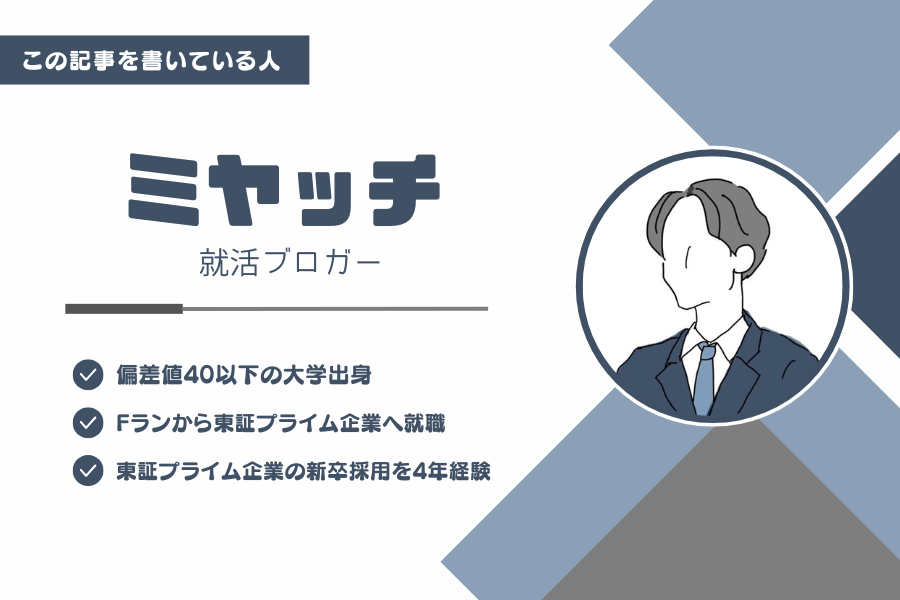はてな
- GDを初めて受けるのですが不安で仕方ない…
- まったく発言できずに撃沈したらどうしよう?
- どういった立ち回りをすれば通過できる?
こんな悩みを解決できる記事を書きました。
GDって「どんなテーマが出題されるのか?」や「メンバーは頭良い人ばかりなのでは?」と不確定要素が多くて不安になりますよね…
私自身、初めてGDを受ける前日は、かなり緊張したのを覚えています。
ただ、偏差値40以下から、GDで無双して「大手グループ・トップ企業」を中心に、下表の成績を残すことができた私が断言します!
| 企業名 | 備考(独自調査データ) |
| 通信系の大手子会社(内定承諾) | 総合職(推定倍率:60.1倍) |
| 住友商事マシネックス(内定) | 総合職(推定倍率:53.1倍) |
| 富士通ゼネラル(内定) | 営業(推定倍率:88.9倍) |
| ニトリ(内定) | 総合職(推定倍率:61.2倍) |
| 東芝テック(内定) | 事務職(倍率:非公開) |
| リクルート(最終選考まで) | 総合職(推定倍率:23.3倍) |
| パナソニック(最終選考まで) | 総合職(推定倍率:94.9倍) |
GDは「事前の調査(カンニング)」と「自分のポジション確保」で無双できます。
今回は、この辺りの具体的な対策を中心に解説していく記事です。
【結論】GDが初めてで不安な人は「情報収集✖️立ち回り」を決める

GDが初めてで不安な人は、「志望企業のGD過去問」を事前にチェックしましょう。
そして、司会のような難易度の高い役割ではなく「タイムキーパー」を選択するのがポイントです!
まずは、この辺りの理由について、詳しく解説していきます!
志望企業の【GD過去問】を事前にカンニング
GD攻略において「去年はどんな感じだったのか?」を知るのは必要不可欠!
「え!志望企業のGD過去問って確認できるの?」と思われた人も多いと思いますが…
だいたいの企業は「ONE CAREER」のような大手就活掲示板に載っています。

ONECAREERの魅力
- インターン口コミが見放題(掲載:58万件以上)
- ES・就活体験談が見放題(掲載:66万件以上)
- 就活対策資料の提供(例:1,000社分の面接質問)
「どんなお題が出るのか」を知っているだけで、当日の緊張は半分以下になります。
私も学生時代に使ってましたが、「ONE CAREER」を一言で言えば、就活における「最強のカンニングペーパー」です。
【公式サイトはこちら】https://www.onecareer.jp/
注意ポイント
「ONE CAREER」で内定者のES・選考情報をすべて見るには「学生証のアップロード」か「大学のメールアドレス」が必要なので事前に準備しておきましょう。
GDでもっとも多い【標準的なタイムスケジュール】
なお、「ONE CAREER」に志望企業のGD情報がなかった人は、下表のスケジュールを参考にしてみてください。
| 時間配分 | やるべきタスク |
| 1分-5分 | 定義付け・前提確認 |
| 5分-15分 | アイデア出し |
| 15分-25分 | グルーピング・整理 |
| 25分-30分 | まとめ・発表準備 |
上表は、多くの企業が採用する「GDの黄金パターン」です。
この表を今すぐスクショして、本番中にスマホのタイマーの横に置いてカンニングしてください。
この流れを知っておけば、「今なにをする時間?」とパニックになることがなくなります。
発言が苦手な人は【タイムキーパー】一択
ここまでの流れを理解したうえで、取るべき役割は「タイムキーパー」です。
とくに、発言に自信がない人こそ、「タイムキーパー」に立候補してください。
おすすめの理由
- 難しいアイデアが一切不要だから
- 発言ゼロを確実に回避できるから
- 時間を告げるだけで「貢献」になるから
例えば、スマホのタイマーを見て、時間を告げるだけで貢献になります。
GDでもっともダメなのは「この学生はまったくGDに参加してないな…」と思われること…
ここを回避する役割として、もっともハードルが低いのが「タイムキーパー」です。
時間がある人は【GD練習イベント】へ参加する
ここまで「知識」をお伝えしましたが、やはりぶっつけ本番はおすすめしないです。
GDが初めてで不安な人は「やったことがないという恐怖心」が影響しています。
だからこそ、本番まで時間がある人は「場数」を踏んでください!
ポイント
- どうでもいい企業のGDで修行
- GDイベントへ参加して恥をかく
- 大学のゼミメンバーで練習する
もっとも本番に近い練習は「どうでもいい企業のGD」へ参加すること!
ただし、ハードルが高いと感じる人は「ジョブトラ![]() 」のような練習イベントに参加しましょう。
」のような練習イベントに参加しましょう。

上図は、私が「ジョブトラ![]() 」に参加したときのイベント風景です。
」に参加したときのイベント風景です。
ゲーム感覚でGDに参加できて、しかも参加企業の人事からフィードバックまでもらえました。
ここで「タイムキーパーの練習」をしておけば、本番は緊張せず楽勝になります。
【公式サイトはこちら】https://job-tryout.com/![]()
注意ポイント
「ジョブトラ![]() 」の予約枠は埋まりやすいので、早めのイベント予約をおすすめします。
」の予約枠は埋まりやすいので、早めのイベント予約をおすすめします。
【役職なしでもOK】偏差値50以上に見せる魔法のフレーズ3選

「まったく議論についていけなかったらどうしよう…」と不安な人は多いと思います。
本章では、そんな人向けの「GDで使える魔法のフレーズ3つ」を紹介します。
役職なしでもOK・ここで紹介するフレーズ3つは頭に入れておきましょう。
議論が止まったときの「整理の合図」
みんなが黙り込んだときこそビックチャンス!
議論が止まったときには、以下のフレーズを使いましょう。
一度、ここまでの意見を整理してみませんか?
これを言うだけで、あなたは「リーダーシップのある人」に見えます。
新しいアイデアを出す必要はなく「整理しましょう」と言うだけでOKです。
難しい言葉が出たときの「教えを請う姿勢」
GDでは、頭の良い学生が「横文字」を多用することがあります。
そのときに、知ったかぶりをして議論を進めるのはやめましょう。
勉強不足で申し訳ないのですが、今の〇〇という言葉について、もう少し詳しく教えていただけますか?
「素直さ」は、新卒採用において「評価基準」となっていることが多いです。
わからないことを聞ける姿勢は、逆に評価アップに繋がります。
意見がないときの「賛成+理由の付け足し」
自分の意見が思いつかないときは、無理に捻り出す必要はありません。
「コバンザメ戦法」を使って乗り越えていきましょう。
私もAさんの意見に賛成です。
理由は、今回のテーマの目的である〇〇に合っていると感じたからです。
ポイントは「賛成です」の後に、「なぜなら〜」を一言付け足すこと!
これだけで、あなたの発言としてカウントされます。
GDで企業が見ているのは「発言回数」ではなく【協調性】

多くの学生が勘違いしてますが、GDは「たくさん発言した人が受かるゲーム」ではありません。
私が新卒採用をしていたときは、発言以上に「協調性」を重点的に確認していました。
発言回数が多いと【クラッシャー認定】の可能性あり
なお、私自身、GDでよく遭遇していたのが「やたら仕切りたがる高学歴風の学生」です!
一見、流暢に喋ってるように見えますが…
クラッシャーの特徴
- 一人で時間を使いすぎる
- 他人の意見を聞かない・否定する
- 結論を急ぎすぎて議論を浅くする
上記のような学生は、企業から「クラッシャー認定」されて間違いなく不合格になります。
組織で働く以上【協調性】はもっとも大切
そのうえで、企業が見ているのは「この子と一緒に働いてみたいか?」という一点のみ!
ポイント
- 相手の意見を否定しない
- 笑顔で相手の話を聞く
- 困っている人に助け舟を出す
GDでは、こういった「協調性のある行動」が好まれます。
なお、株式会社SynergyCareerによる「GDに関する調査」でも、学生が企業から求められていると感じたことの1位が「協調性」でした。
こういった統計データ上でも「協調性」が大切と書かれています。
【要注意】GDでやってはいけない行動3選

本章では、これだけは絶対にやってはいけない行動にふれていきます。
本番で「やってしまった…」とならないように事前に押さえておきましょう。
GDでやってはいけない行動【3選】
- 地蔵化(まったく発言をしない・相槌すらしない)
- 否定発言(相手の意見を潰す)
- 時間切れ(結論が出ないまま終わる)
地蔵化(まったく発言をしない・相槌すらしない)
詳しくは「GDで喋らないでも受かる理由3選」という記事で紹介していますが…
GDで喋らなくても受かることはあります!
ただし、発言がまったくないと、企業も採点しようがありません。
ポイント
- 発言者に椅子を傾けて相槌する
- 賛成・反対などの意見は述べる
- 発表まで残り〇〇分ですと告げる
まったく発言しない「地蔵化」になるのではなく、少しでも発言・傾聴する姿勢は見せましょう。
否定発言(相手の意見を潰す)
また、「いや、それは違うと思います!」という発言も使わないようにしましょう。
例え、相手が間違った発言であっても、協調性のマイナスになる行動はおすすめしません。
「なるほど、そういう視点もありますね。ただ、今回の目的から考えると〜」!
上記のような、イエス・バット(Yes, But)法を用いて、自分の意見を言うようにしましょう。
時間切れ(結論が出ないまま終わる)
GDは「結論を出すこと」がゴールです。
議論が盛り上がり、時間内に答えが出なかった場合、チーム全員が不合格になることもあります。
だからこそ、先ほど紹介した「タイムキーパー」という役割が大切です。
あなたが時間を管理し、チームを合格へ導いてください。
GDが初めてで不安な学生からのよくある質問【3選】

最後に、皆さんが気になっている「意見がまったく思いつかないときは?」のような質問に一問一答方式でお答えします。
よくある質問【5選】
- 意見がまったく思いつかないときは?
- 時間内に結論が出なかったら全員落ちる?
- ぶっつけ本番でもなんとかなる?
質問①:意見がまったく思いつかないときは?
N氏(21歳)
GDで意見が思いつかないときはどうすべきでしょうか?
具体的な対処法を教えて欲しいです…
GDで意見が思いつかないときは、「相手の意見に乗っかる」ようにしてください。
例えば、「私も〇〇さんの意見に賛成です」と声にするだけでも違います。
また、「賛成した理由は〇〇だからです」と理由を付け足すように意識しましょう。
0から1を生み出すのが苦手であれば、1を10にするサポート役に徹すればOKです。
質問②:時間内に結論が出なかったら全員落ちる?
N氏(22歳)
GDのテーマで結論が出せなければ全員落ちますか?
受けた企業で結論まで至らなかったことがあります…
結論、100%落ちるわけではありません。
ただし、まったく発表できないレベルの内容であれば落ちます。
企業は、「テーマに対する答えではなく過程」を大切にしているのも事実!
途中までの場合も「〇〇まで調査・分析しました」という姿勢は見せましょう。
質問③:ぶっつけ本番でもなんとかなる?
T氏(20歳)
GDはぶっつけ本番でもなんとかなりますか?
選考が明日に迫っているので出来ることがありません…
正直、GDをぶっつけ本番で挑戦するのはおすすめしません。
私の経験上、GD攻略のカギは「どれだけ場数を踏むか」です。
一度でも経験していれば、周りがよく見えますが、初めてだとパニックになって終わります。
そのため、今回紹介した「ジョブトラ![]() 」などの無料イベントで、1回でも良いので「場数」を踏んでおくことを強くおすすめします。
」などの無料イベントで、1回でも良いので「場数」を踏んでおくことを強くおすすめします。
【公式サイトはこちら】https://job-tryout.com/![]()
まとめ|GDが初めてで不安な人は「情報収集✖️立ち回り」を決める
今回は、「GDが初めて受けるけど不安で仕方ない…」という悩みを中心に紹介しました。
そもそも、不確定要素が多いGDが怖いのは当たり前です。
私自身、GD前日は胃が痛くなるくらいに緊張していました。
ただし、今回紹介した「過去問のカンニング)」と「自分のポジション確保」でGDは無双できます。
本記事の要点
- 志望企業の過去問を「ONE CAREER」で確認
- GD全体の流れを頭に入れておく
- 発言できる自信がなければ「タイムキーパー」を選ぶ
GD前日に上記3つを押さえているか否かで通過率は大きく変わります。
あとは、GDまで2週間くらいの時間があれば、「ジョブトラ![]() 」などの無料イベントで「場数」を踏んでください。
」などの無料イベントで「場数」を踏んでください。
GDの不安をかき消すためにもっとも効果があるのは「場数を踏むこと」です!
以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。