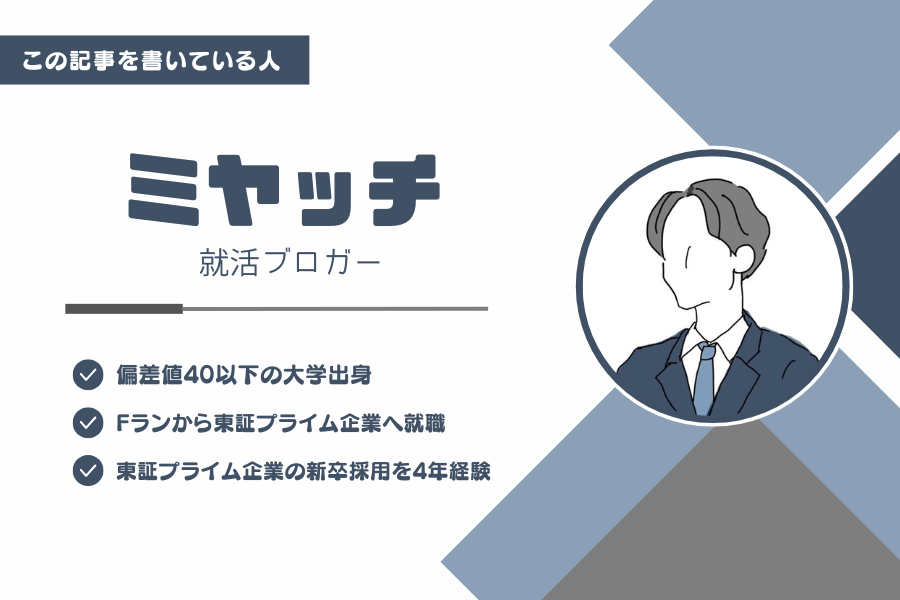本記事で分かること
- 早期選考を準備不足でも受けるべき理由【3選】
- 早期選考を受けるべき人・受けるべきでない人
- 早期選考までに最低限やるべき事前準備【5選】
結論、早期選考は準備不足でも受けるべきです。
私自身、「企業研究が不十分かも…」と思いつつ、今では受けて良かったと思っています。
ただし、早期選考で落ちると「本選考へ応募できなくなる」場合は例外です。
準備不足で落ちる確率が高い以上、無理に受ける必要はありません。
「誰でもできるFランから大手が目指せる就活テクニック15選」を参考にしつつ、本選考に向けた事前準備を進めていきましょう!
なお、それ以外の人であれば、「早期選考を受けるメリット」は多いので挑戦すべきです。
今回は、そんな「早期選考を準備不足でも受けるべき理由3つ」について紹介していきます!
【実体験】早期選考を準備不足でも受けた理由3選

ではさっそく、私が「早期選考を準備不足でも受けた理由3つ」を紹介します。
なお、私は早期選考に「面接練習なし」で挑戦するくらい準備不足でした。
早期選考を準備不足でも受けた理由【3選】
- 早期選考は受かりやすい
- 本選考前の実践経験になる
- 選考免除の優遇があった
理由①:早期選考は受かりやすい
詳しくは、「早期選考は受かりやすい?」という記事で紹介していますが…
以下3つの理由から、早期選考は受かりやすいです。
- 選考免除のケースが多い
- 選考の評価基準が緩い
- 採用枠が多い
とくに、「選考の評価基準が緩い」のが早期選考の特徴の一つ!
人事としては「まずは採用目標を達成したい」という心理が働きます。
そのため、早期選考という学生採用のスタート時期には、選考の評価基準が緩くなりがちです。
本選考よりチャンスがある以上、準備不足でも積極的に挑戦すべきと考えます。
合わせて読みたい
理由②:本選考前の実践経験になる
私の中で、「本選考前の実践経験」になったのが早期選考でした。
- エントリーシートの提出
- グループディスカッション
- 集団面接・個人面接など
一部、選考免除されることもありますが、「二次面接・最終面接」は受けることがほとんどです。
本選考前に「面接経験があるFラン学生」と「早慶上智で初めて面接を受ける人」であれば、Fラン学生が優位に立てる可能性は十分にあります。
私自身、こういった思考で早期選考へ参加し、実際に受けて良かったと感じました。
理由③:選考免除の優遇があった
早期選考は「インターンシップ」や「逆求人サイト」経由で招待させることがほとんどです。
その中で、以下のような「選考優遇」を受けられることがあります。
- エントリーシートの再提出が不要
- WEBテストの免除
- 一次・二次面接の免除
事実、私は「エントリーシートの免除」が特典としてありました。
準備不足という不安要素はありましたが、私が早期選考を受けた理由の一つです。
なお、選考免除のあった企業は、最終的に「大学3年12月に内々定」という結果でした。
こういった理由からも、私は準備不足でも早期選考へ挑戦すべきと考えています。
【実体験】早期選考へ参加するデメリット3選

本章では、「早期選考へ参加するデメリット」についてまとめました。
大きく3つに分けて紹介していくので、合わせてチェックしておきましょう!
早期選考へ参加するデメリット【3選】
- 本選考に応募できない
- 厳しい目線で審査される
- 自信喪失の可能性がある
デメリット①:本選考に応募できない
繰り返しになりますが、早期選考で落ちると「本選考に応募できない」ケースがあります。
そのため、本選考への再応募可否は事前確認が必要不可欠!
早期選考に自信がなければ、本選考に照準を合わせるのも一つの手です。
デメリット②:厳しい目線で審査される
早期選考で落ちた場合、本選考で「審査の目が厳しくなる」ケースも存在します。
「早期選考で落ちた=何かしらの懸念点があった」ということです。
つまり、企業は「一度見送った学生」である以上、「その理由を克服しているか?」を注視します。
そのため、「なぜ早期選考で落ちたのか・何を改善すべきか」事前に整理するのは必要不可欠!
- ガクチカ・自己PRの内容は浅くないか
- 志望動機に具体性・企業理解はあったか
- 面接での話し方・印象に問題はなかったか
もちろん、早期選考の不合格は、成長のチャンスでもあるので前向きに捉えましょう。
デメリット③:自信喪失の可能性がある
早期選考で落ちた学生の中には、自信喪失する人も少なくないです。
結果、本選考の対策に身が入らないというケースは珍しくあります。

- 就活から離れる
- 落ちた企業のイヤな部分を探す
- とにかく就活に専念する
上記は、私が最終面接で落ちたときのメンタル回復方法です。
詳しい詳細は、以下記事にまとめているので「ブックマーク」して後から見返せるようにしておきましょう。
合わせて読みたい
早期選考を準備不足で受けるべきではない人【2選】
本章では、「早期選考を準備不足で受けるべきではない人」について紹介します。
ここまでの内容をふまえ、大きく2つにまとめたのでチェックしてみてください!
早期選考を受けるべきではない人【2選】
- 本命企業の早期選考
- まったく就活対策していない人
特徴①:本命企業の早期選考
「本命企業の早期選考」であれば、事前準備なしで受けることをおすすめしません。
とくに、以下2つに当てはまる場合は、100%受けないようにしましょう。
- 早期選考で落ちたら再応募できない
- 選考優遇を受けているわけではない
正直、本選考までに「入念な準備」をしたほうが受かる確率は高いです。
特徴②:まったく就活対策していない人
先ほども紹介しましたが、以下3つの理由から「早期選考は受かりやすい」です。
- 選考免除のケースが多い
- 選考の評価基準が緩い
- 採用枠が多い
ただし、就活対策をまったくしていないまま受ける場合は例外です。
「自己PR・ガクチカがない」といったレベルであれば100%受かりません。
早期選考が受かりやすいとは言え、記事後半で紹介する「早期選考を受けるために最低限やるべき事前準備5つ」は必要不可欠です!
早期選考を準備不足でも受けるべき人【3選】

続けて、「早期選考を準備不足でも受けるべき人」について紹介します。
ここまでの内容をふまえ、大きく3つにまとめたのでチェックしてみてください!
早期選考を受けるべき人【3選】
- 選考優遇がある人
- 本命企業の早期選考ではない人
- 早期内定を目指している人
特徴①:選考優遇がある人
以下のような「選考優遇のある早期選考」であれば受けることをおすすめします。
- エントリーシートの再提出が不要
- WEBテストの免除
- 一次・二次面接の免除
選考免除がある以上、早期選考を受けない手はありません。
多少準備不足であったとしても、本選考に比べて有利なのは間違いありません。
特徴②:早期内定を目指している人
早ければ「大学3年の2月まで」に内々定を狙えるのが早期選考です。
そして、早期内定には、以下3つのメリットがあります。
メリット
- 就活への不安・焦りが激減する
- 学生生活の自由度が上がる
- ほか企業の面接官からの評価が上がる
とくに、「就活への不安・焦りが激減する」のが最大のメリットです。
私自身、大学3年12月に1社の内々定を獲得した結果、本選考はリラックスして挑戦できました。
また、志望企業の面接官へ「すでに内定1社あるのか!」と印象づけられたのもポイントの一つ!
本選考前に「内々定という武器」を装備するうえで、早期選考への挑戦は必要不可欠です。
特徴③:本命企業の早期選考ではない人
本命企業の早期選考ではない場合、挑戦しておいて損はありません。
例え準備不足で落ちたとしても、以下のようなノウハウが蓄積されます。
- エントリーシートを書く難しさ
- WEBテストの受験方法
- 面接の緊張感・回答の仕方
私自身、面接練習なしで早期選考に挑戦して落ちた側の人間です。
ですが、本命企業ではなかったので後悔はありません。
逆に「このままではやばい!」と本選考前に気合いが入ったのを覚えています。
以上が、私の考える「早期選考を準備不足でも受けるべき人」の特徴です。
早期選考を受けるために最低限やるべき事前準備【5選】
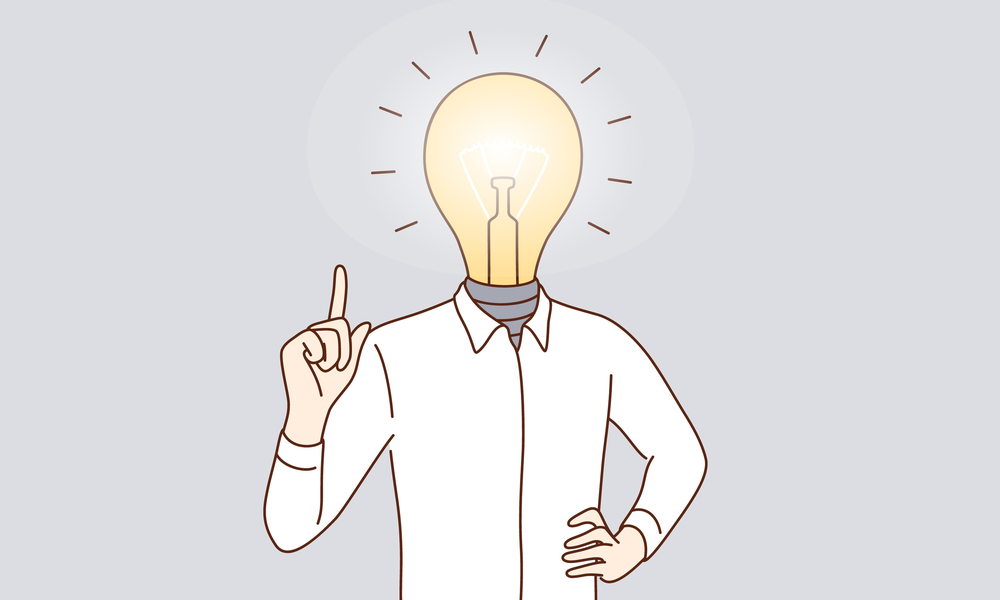
「早期選考を受けるために最低限やるべき事前準備」は合計5つです。
面接練習なしで挑戦した私だからこそ、以下5つはやっておくべきと確信しています。
早期選考を受けるために最低限やるべき事前準備【5選】
- 自己分析
- 企業研究
- 自己PRの作成
- ガクチカの作成
- 面接対策
準備①:自己分析
早期選考を受けるにあたり、「自己分析」は必要不可欠です。
自己分析が必要な理由
- あなたという商品を知るため
- 自己PR・ガクチカ作成に必要なため
- 自分に合った業界・企業を見つけるため
「自分に合った業界・企業を見つけるため」という理由も大切ですが…
何よりも、就活における「あなたという商品理解」に必要不可欠です!
あなた自身の強みを理解し、「精度の高い自己PR・ガクチカ」を作り上げていく必要があります。
なお、昨今は生成AIをうまく活用すれば「自己分析」は簡単にできる時代です。
自己分析がまだの人は、以下記事を参考に取り組んでおきましょう!
合わせて読みたい
準備②:企業研究
早期選考を受けるにあたり、「企業研究」も必要不可欠です。
企業研究の必要性
- 志望動機の精度向上
- 面接官の質問に的確に答えるため
- 企業が求める人物像の明確化
上記のとおり、企業研究の深さは、「志望動機」や「面接の受け答え」に直結します。

私は、どんな環境でも主体的に価値を生み出せる人材になりたいと考えています。とくに、学生時代に〇〇に挑戦した経験から、「正解のない課題に挑む力」を身につけました。貴社では、20代から圧倒的な裁量とスピード感で事業づくりに携われる環境があり、私の「逆転キャリアを築きたい」という想いと強く重なりました。
正直、上記レベルの志望動機であれば、リクルート社の選考は100%落ちます。
「挑戦できる環境を求めるならベンチャーでも良いのでは?」と思われるからです。
だからこそ、以下のような「リクルートでないとダメだ!」という志望理由が必要不可欠!
私は「人と社会を前に進めるような事業づくり」に挑戦したいと考えています。学生時代、〇〇に取り組む中で「情報の非対称性が人の選択肢を狭めている」ことに問題意識を持ちました。この課題に対し、貴社は「マッチングテクノロジー」と「圧倒的な意思決定スピード」で、既存の仕組みを変革し続けています。単なる裁量だけでなく、「社会課題に事業で挑む」という思想に強く共感し、貴社でキャリアを築きたいと考えました。
ここを明確にするために「企業研究」はかならず実践しておきましょう。
自己分析と同じく、昨今は生成AIの誕生で「企業研究」も簡単にできる時代です!
合わせて読みたい
準備③:自己PRの作成
早期選考において「自己PRの作成」は確実に求められます。
どれだけ準備不足でも、自己PRは作成して挑戦するようにしましょう。

- あなたのアピールしたい強み
- 根拠となるエピソード
上記2つは、「生成AI」を上手く活用すれば見つけることができます。
自己PRに書けるエピソードがない人は、以下記事を参考に作成してみてください!
合わせて読みたい
準備④:ガクチカの作成
早期選考において「ガクチカの作成」も確実に求められます。
もし、早期選考の時点で「ガクチカに書けるエピソード」がなければ、無理矢理作りましょう。
- 派遣の単発アルバイト
- ゼミ教授の手伝いをする
- 生成AI使って授業を受ける
上記のとおり、探せばいくらでもガクチカのエピソードは見つかります。
そのうえで、以下4つを実践すれば「精度の高いガクチカ」を作成できます。
ガクチカ作成の進め方
- ガクチカの正しい構成を学ぶ
- 大手内定者のガクチカを見る
- 生成AIを用いて下書き作成
- 第三者に意見をもらう
なお、早期選考まで「1ヶ月以上」ある人は、「単位と関係ない授業を受けてガクチカに書く」のがおすすめです。
この辺りの詳しいやり方は、以下記事で紹介しているので参考にしてみてください!
合わせて読みたい
準備⑤:面接対策
私自身、早期選考を受けた1社目は「面接練習なし」で挑戦しました。
当たり前の話ですが、面接官の質問にまったく対応できずに大惨敗…
私の経験上、早期選考の参加前に以下5つは実践しておきましょう。
- 面接マナーのチェック
- 企業調査の徹底
- 提出書類の読み込み
- 想定質問への回答準備
- 逆質問の事前準備
なお、各面接フェーズによって対策する内容に違いがあります。
もし上記5つ含め、面接対策をまったくしていない人は、以下記事を参考に対策してみてください。
合わせて読みたい
早期選考に関するよくある質問【5選】

では最後に、早期選考へ参加すべきか悩んでいる学生からのよくある質問5つを紹介します。
ぜひ、気になる質問があればチェックしてみてください。
早期選考に関するよくある質問【5選】
- 早期選考は何社受けるべき?
- 早期選考の合格率は?
- Fラン学生も早期選考は受けるべき?
- 早期選考はどうやって受けるの?
- 早期選考に受かるための対策は?
質問①:早期選考は何社受けるべき?
R氏(21歳)
早期選考は何社くらい受けるべきですか?
周囲に早期選考を受ける学生がいないので悩んでいます…
結論、早期選考を何社受けるべきか明確な数字はありません。
ただし、私の経験上は「5社以上(理想は10社)」受けるのがおすすめです。
「就職みらい研究所」によると、26卒の大学3年2月時点の就職内定率は39.3%!
早期選考の通過率は100%ではないので、「受けた社数=チャンス」につながります。
そのため、5社以上・理想は10社を目安に挑戦してみてください!
質問②:早期選考の合格率は?
T氏(20歳)
早期選考の合格率はどれくらいですか?
早期選考が受かりやすいというウワサを耳にしました。
結論、早期選考の合格率は39.3%前後です!
詳しくは、「早期選考の合格率は?」という記事で紹介していますが…
| 選考ステップ | 早期選考 | 本選考 |
| 書類+WEBテスト | 70%前後 | 50%前後 |
| 一次面接(GD含む) | 60%前後 | 50%前後 |
| 二次面接 | 60%前後 | 30%前後 |
| 最終面接 | 90%前後 | 50%前後 |
私の感覚値としては、各選考の中でも「一次・二次面接」が鬼門のイメージです。
ただし、早期選考は「選考免除」という優遇を受けやすいのも事実!
合格率はあまり気にせず、積極的に挑戦することをおすすめします。
質問③:Fラン学生も早期選考は受けるべき?
N氏(21歳)
Fラン学生も早期選考は受けるべきですか?
早期選考に学歴フィルターがないか心配です…
結論、Fラン学生こそ早期選考に挑戦してください!
「早期選考は受かりやすい?」という記事の後半で詳しく紹介していますが…
早期選考を受けるべき理由
- 本選考前に内定獲得のチャンスがある
- 本選考前に実践経験が積める
- 学歴フィルターが少ない
偏差値40以下の私自身、早期選考に参加して上記3つの恩恵を実感しました。
そのため、Fラン学生こそ早期選考には積極的に挑戦しましょう。
合わせて読みたい
質問④:早期選考はどうやって受けるの?
S氏(19歳)
早期選考に挑戦したいのですがどうやって受けるの?
マイナビ・リクナビ経由で探すのが良いのでしょうか?
結論、早期選考を受けるには、以下5つの実践が必要不可欠です。
- 逆求人サイトの導入
- サマーインターンへの参加
- 就活エージェントへ相談する
- 就活イベントへ参加する
- 大学の学内セミナーへ参加する
とくに、「逆求人サイトの導入」と「就活イベントへの参加」は必要不可欠!
詳しい詳細は、「早期選考はどうやって受けるの?」という記事で紹介しています。
早期選考が受けられる企業の探し方を知りたい人は、ぜひ参考にしてみてください!
質問⑤:早期選考に受かるための対策は?
N氏(19歳)
早期選考に受かるための対策を教えてください!
正直、就活対策をまったく進めていません…
早期選考で受かるには、「早く就活を始める」のが鉄則です。
早期選考まで時間のある人は、以下15つのステップに沿って対策を進めていきましょう。
- ステップ①:就活サイトの整理・導入
- ステップ②:生成AIの導入
- ステップ③:自己分析の実施
- ステップ④:業界研究の実施
- ステップ⑤:企業研究の実施
- ステップ⑥:OB・OG訪問の実施
- ステップ⑦:自己PRの作成
- ステップ⑧:ガクチカの作成
- ステップ⑨:逆求人サイトの導入
- ステップ⑩:WEBテスト対策
- ステップ⑪:志望動機の作成
- ステップ⑫:面接対策
- ステップ⑬:サマーインターンへの参加
- ステップ⑭:冬のインターン参加
- ステップ⑮:早期選考への参加
上記15ステップは、私がFランから大手に内定した就活テクです。
以下記事で、具体的なやり方を紹介しているので合わせてチェックしてみてください!
【まとめ】早期選考は準備不足でも積極的に受けよう
今回は、早期選考は準備不足でも受けるべき理由を中心に紹介しました。
早期選考を準備不足でも受けた理由【3選】
- 早期選考は受かりやすい
- 本選考前の実践経験になる
- 選考免除の優遇があった
上記は、私が早期選考を準備不足でも受けて良かった理由3つです。
とくに、「本選考前の実践経験になった」という理由がおすすめポイントの一つ!
大学3年生の12月くらいから「実践経験」を積めたのは大きかったです。
そのため、早期選考を受けるべきか悩んでいる人は、積極的に挑戦してみてください。
早期選考まで時間がない人は、記事内で紹介した「早期選考までに最低限やるべき事前準備5つ」!
早期選考まで余裕のある人は、以下記事の内容を一つずつ実践していきましょう。
以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。